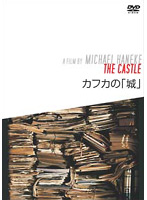父と暮せば
 | 父と暮せば 通常版 2004年/日本/99分 監督・脚本:黒木和雄 原作:井上ひさし 撮影:内田絢子 美術:木村威夫 音楽:松村禎三 出演:宮沢りえ、原田芳雄、浅野忠信、他 Amazonで詳しく見る |
黒木和雄監督作品は初めてですが、観ていて複雑な気持ちになる映画だった。
まず気になったのはこの映画は戦争を扱ったフィクション映画だが、その戦争に対する視線が「被害者一色」であったこと。「お涙頂戴」であったこと。
これは原作の井上ひさし氏によるところが大きいとは思うが、この映画自体の進展性に歯止めをかけていることは否めない。興行的でない日本の戦争映画を観るといつも感じることだが「戦争体験を語り継ぐため」にわざわざ映画を作るのはコスト的にもバカバカしく感じる。やはり忘れてならないのは「戦争の記憶」ではなく「2度と戦争を起こさないこと」「何故戦争になってしまったのか」ということで、これはいろいろな国の事情が絡み合っているので色々な側面からのクレームなど一筋縄にはいかないだろうが、これを描かなければ「語り継ぐ」意味はほとんどない。
簡単なヒューマニズムで涙を誘っても満足させれるのは、戦争の記憶を持ち続けている60代くらいの例えば岩波ホールに足を運ぶ人々や、あるいは、戦争に対して具体的に何も行動しない人たちだけで、そういう意味では結果的に「反戦」がテーマなはずの戦争映画なのにその効力がほとんどなくなってしまっている。この映画は感傷的になることを強要し、戦争を起こさないよう考えることを禁じている変な映画だ。
ただ、上記の制限は脚本の制限であったようにも思う。
台本段階でできることとできないことがハッキリとするとは思うが、撮影段階では可能なできることは丁寧にすべてやってある印象も同時に持った。小規模な予算を想像すると、驚くほどこの映画のクオリティーは高い。
プロット的には90年代のハリウッドの恋愛映画「ゴースト ニューヨークの幻」を彷彿とさせるような見せ方を戦争ものに取り入れた井上ひさし氏の功績も大きいように思う。
それとこの「父と暮らせば」はファーストカットから「演劇的な演出のスタジオ撮り」だったが、街に出て撮影できれれば、パッケージとしての完成度は落ちるものの、違った作風の映画らしい映画になったかもしれないなどと考えてみたり。。