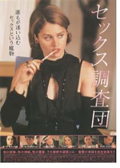コーヒー&シガレッツ
 | コーヒー&シガレッツ Coffee and Cigarettes 2003年/アメリカ/97分 監督・脚本:ジム・ジャームッシュ 出演:ロベルト・ベニーニ、ジョイ・リー、イギー・ポップ、トム・ウェイツ、ジョー・リガーノ、ルネ・フレンチ、E.J.ロドリゲス、ケイト・ブランシェット、メグ・ホワイト、ビル・マーレー、スティーヴ・ブシェミ、スティーヴ・クーガン、他 Amazonで詳しく見る |
この映画を観ると「映画とは何ぞや!!」といった鯱ばった考えが哀れに思えてくるくらい「さらり」と、なぜか観て不満を感じさせない映画となっている。
この映画「コーヒー&シガレッツ」は1986年から11本の短編を「コーヒー(紅茶)とタバコ」というテーマで、かつ、ほぼ同一のカット割りで魅せる連作集。
観ていて面白かったのはマイケル・ウインターボトム監督の「24アワー・パーティー・ピープル」でトニー役を演じたスティーヴ・クーガンが出ている「Cousins? いとこ同士?」。
クーガン氏の胡散臭さが絶妙にその小話に収斂されており、会話のやり取り、というか、その駆け引きがユーモラスで印象深い。
欲をいえば11編の連作のなかで「コーヒーとタバコ」以外の人間の根源的かつ抽象的な、「人生とは何か」というようなヒューマニズム的なものにおさまらないような、一貫したテーマがあって、このようなユーモラスな後味を残せたならば映画史に残る作品になるとは思うけれど、この映画の持ち味と両立しえないかな。
あとこの映画は本国では2003年の製作だが日本公開は05年。仮にこの映画に配給がなかなかつかなかったのかと考えると心苦しくなる。
このモノクロ映画は「単館系」とはいえ「ジャームッシュ監督作品」という名前はあるものの美術館で上映するような芸術ではなく、かといって大ヒットも見込るようなエンタテイメント映画でもない、純=映画が、他の安い志のドラマと比べて「商品」として成立しずらいことは、そんな映画ばかりが好きな私には小さな希望がより小さくなってしまうような気持ちにさせる、なんてことを考えてしまったり。
なお、公式サイトでは9種類の壁紙のダウンロードなどができる。
「コーヒー&シガレッツ」公式サイト
http://coffee-c.com/