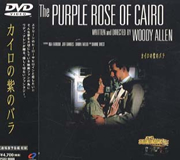やわらかい生活
 | やわらかい生活 スペシャル・エディション 2006年/日本/126分 監督:廣木隆一 プロデューサー:森重晃 原作:絲山秋子「イッツ・オンリー・トーク」(文藝春秋) 脚本:荒井晴彦 撮影:鈴木一博 音楽:nido 出演:寺島しのぶ、豊川悦司、松岡俊介、田口トモロヲ、妻夫木聡、大森南朋、柄本明、他 Amazonで詳しく見る |
脚本は「ヴァイブレータ」と同様に荒井晴彦氏が担当。主演も「ヴァイブレータ」に引き続き寺島しのぶさんが務め、脇を豊川悦司さん、松岡俊介さん、田口トモロヲさん、妻夫木聡さん、大森南朋さん、柄本明さんなど確かな演技の男優達がしめる、逆ハーレム的な意味で寺島しのぶさんにとって贅沢なキャスティング。
廣木隆一監督作品というと、「撮るテーマに対して距離をとる」印象があり、そこがクールさにつながっているような作品が多いが、今回はらしからぬ感じが出ていて、逆に好印象。名実ともに演出プランは「ヴァイブレータ」の延長線上にあることが感じられる。
絲山秋子氏の原作は読んでいないが、寺島しのぶさん演じる役柄のような30代女性は自分の周りに多いような気がした。役中の設定も早稲田卒だったが、「気づかないうちに生きていくのが苦しくなってしまった30代女性」などには癒しの1本となる映画のような気がする。
相手役の豊川悦司さんもそういう意味ではハマリ役なような気がする。一方で、松岡俊介さんと妻夫木聡さんは役柄が逆な方が自然だった感がある。このキャストは冒険といえばそうだが、冒険する必然を観ていて感じなかったのは少し残念な点。
個人的には撮るテーマを真摯に追い求めるような映画が好きな私にとっては、この「やわらかい生活」は廣木隆一監督作品の中でナンバーワンだ。
「やわらかい生活」公式サイト
http://www.yawarakai-seikatsu.com/