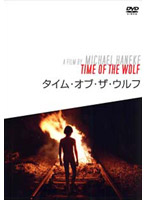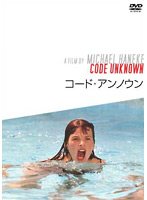セブンス・コンチネント
 | セブンス・コンチネント DER SIEBENTE KONTINENT THE SEVENTH CONTINENT 1989年/オーストリア/111分 監督・脚本:ミヒャエル・ハネケ 製作:ファイト・ハイドゥシュカ 撮影:トーニ・ペシュケ 出演:ビルギッド・ドール、ディーター・ベルナー、ウド・ザメル、ゲオルク・フリードリヒ、他 Amazonで詳しく見る |
「ファニーゲーム」ほど不条理ものではないが、悪いほう悪いほうへ進む様はむしろ圧巻。
銀行に貯金していたお金を小銭も含めて水洗便所に流す長回しなどは、登場した家族の社会的価値への徹底的な抵抗に見られ、見る者に「何をそこまで思い詰めて」と感じさせるストイックさだ。
具象の世界から砂嵐に至るまでの過程が描かれた稀有な映画。
こういう映画を観ていると「言葉攻め」プレイを思い起こさせる。
「本当にこれでいいのか? ・・・そうじゃないだろう。」
というようなハネケ監督の言葉が聞こえてきそうである。
映画などの作品には「直接言語的映像」を使い、登場人物の目線のカットをふんだんにもちいた「体験型映像(AVで言えばハメ撮り)」がある一方で、物語などのプロットを使いながら何かを指し示す「間接言語的映像」があることを想起させられる。簡単に言えば、善くも悪くも「説教されている」ような感じの映画でした。本当に。
ちなみに「第7の大陸=セブンス・コンチネント」は実際には存在しない、架空の大陸のこと。