去年マリエンバートで
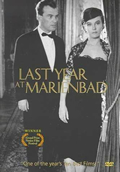 | 去年マリエンバートで L'anne'e dernie're a' Marienbad 1960年/フランス・イタリア/94分 監督:アラン・レネ 原作・脚本:アラン・ロブ・グリエ 撮影:サッシャ・ヴィエルニー、音楽:フランシス・セイリグ 出演:デルフィーヌ・セイリグ、ジョルジュ・アルベルタッツィ、サッシャ・ピトエフ、他 Amazonで詳しく見る |
しかもうっとりさせるのは言葉だけでななくデルフィーヌ・セイリ(ン)グの造形的な美貌にある。彼女が女優として優れているかはわからないが、ちょうどレオス・カラックス監督の「ボーイミールガール」のミレーユ・ペリエのように彼女の魅力は色あせない。ちょうど2本ともモノクロ作品であることを考えると、実物+ブラック&ホワイト特有の幻想感が混ざり合っているのかもしれない。
それに加え、原作・脚本のアラン・ロブグリエは後に自身で「消しゴム」など様々な作品の監督もつとめているが、ぬるい心理描写などを一切排除したストイックな脚本は完璧な撮影監督によって映画化されている。撮影監督のサッシャ・ヴィエルニーは後に「ZOO」「コックと泥棒、その妻と愛人」「プロスペローの本」などピーター・グリーナウェイ監督作品群の撮影を担当している。
そして監督のアラン・レネ。「ヒロシマ・モナムール」(24時間の情事)や「夜と霧」などが有名だが、初期のアラン・レネ作品は野心がありかつ実験色が強い作品を発表し続けておりどの作品も目が離せない。
これら全てが一つの作品に収まっているような映画は他に存在しないし、これからもないだろう・・・。
ちなみにこの映画のDVDは現在廃盤となっており、このサイトでリンクを貼っているアマゾンでは、中古で2万5000円くらいで取引きされているかなりのレアもののようだ。




